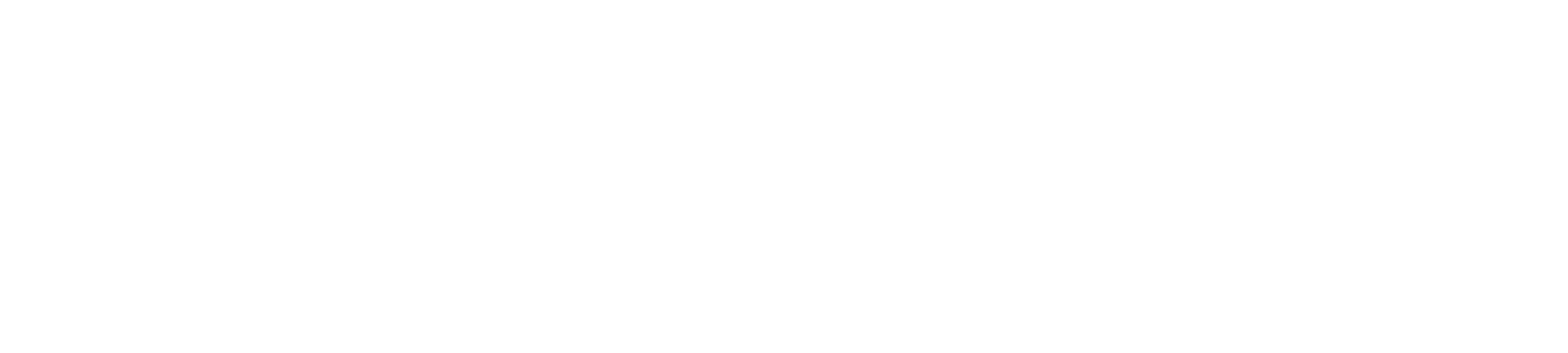京都大学経営管理大学院・経済学研究科は、令和7年7月26日に第115回京都管理会計研究会を総合研究2号館にて開催しました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、山田 善紀氏(甲南大学経営学部 非常勤講師、公認会計士、税理士)、及び、池田 聡氏(桜美林大学 准教授)より「サステナビリティ関連情報開示と企業価値(株式時価総額)との関連性にかかる実証研究」と題して報告し、出席者と議論しました。
本研究の狙いは、企業が開示するサステナビリティ関連情報(たとえば人的資本への投資や研究開発の取り組み)が、市場で評価される会社の価値=時価総額とどの程度結びつくかを確かめることにあります。データは、人材活用に力を入れる企業群である「JPX日経 人的資本100」を主な対象とし、相関・回帰分析を行いました。
分析の土台は、Ohlsonモデルです。これは、「会社の価値=帳簿上の純資産+将来の上乗せ利益(異常利益)の割引現在価値」というもので、異常利益は、「t+1期の予想利益 ― t期の純資産×資本コスト(8%)」として定義されます。異常利益は、「超過収益力」、「その他の情報」からなるとされており、本研究は、研究開発費といった無形資産投資や人的資本投資に関する情報が、企業価値決定の要素となる「その他の情報」なのではないか、という期待を込めています。異常利益は5年もしくは10年で薄れると仮定し、現在価値に割り引いて合計されます。あわせて、研究開発費や人件費といった“人と技術への投資“も説明変数として加えられ、モデルの説明力を比較しています。
主な結果として、異常利益と時価総額のつながりがこの数年で非常に強くなったことが確認されました。また、研究開発費や人件費といった“人と技術への投資”をモデルに加えると、概ね相関が高くなることが確認されました。言い換えると、投資家はいまの資産の大きさだけでなく、将来どれだけ上乗せで稼げるか、その裏付けとなる人材・技術投資の情報を重視する、という示唆です。
本研究は、サステナビリティ関連の開示、特に人や技術への投資を示す定量情報が、企業の将来の稼ぐ力を通じて時価総額と深く結びつく可能性を示しました。企業にとっては、単にスローガンを掲げるのではなく、どれだけ人材育成や研究開発へ資源を振り向け、その成果をわかりやすく開示するかが、投資家との対話と評価向上の要になる、という実践的な示唆が得られます。
参加した約15名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論がかわされ、盛会のうちに終了しました。