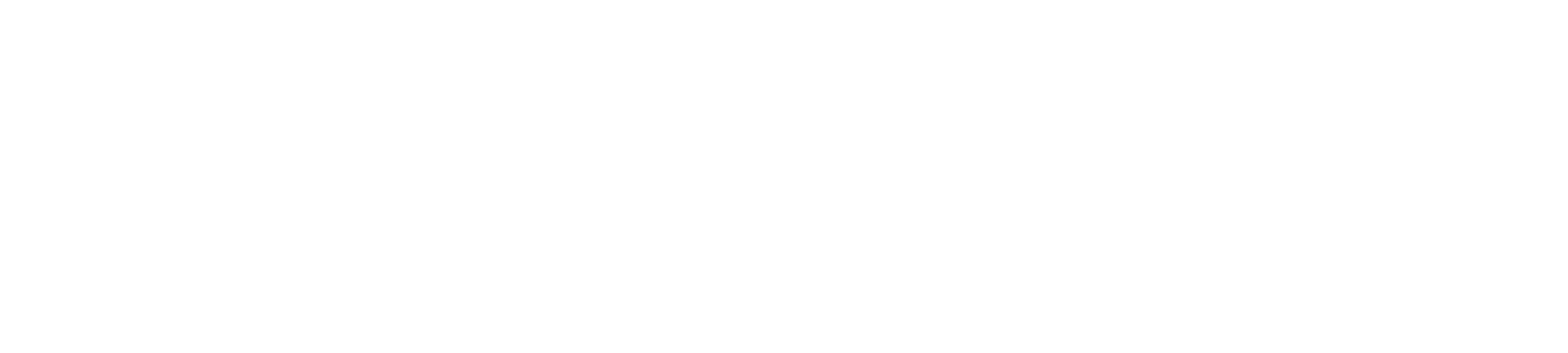京都大学経営管理大学院・経済学研究科は,令和7年6月30日に第114回京都管理会計研究会をTOKYO-YOKOHAMA INTERNATIONAL MINI-CONFERENCE 2025との共催で京都大学東京オフィスにて開催しました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、4つのセッションに分けて報告が行われました。
第一部ではKeynote SessionとしてZachary Mohr氏(The University of Kansas, School of Public Affairs and Administration, Associate Professor)より、「Behavioral-Experimental Budgeting Revisited-The Evolution of Experiments in Public Budgeting Research-」と題して講演しました。本講演では、ハーバート・サイモンが視察した地方自治体の予算編成過程に基づき、人間は限界便益に基づく合理的意思決定が困難であるとし、「限定合理性」の概念を提唱した経緯を以下のとおり説明しました。 従来の経済学が限界利益の比較衡量によって人間は合理的に意思決定するという前提を批判的に検討し、社会科学が実際の人間の行動観察へと進む契機となりました。さらにダニエル・カーネマンらによるプロスペクト理論やナッジ理論に代表される行動経済学の発展が、公共予算の研究にも応用され、実験的手法を導入したBehavioral Budgeting の研究が始まりました。従来、公共予算の研究では仮想シナリオ(vignette)による調査に依存してきましたが、近年はシミュレーションの活用が進んでいます。特に予算シミュレーションでは、税と支出の調整を住民に体験させることで、意思決定行動を可視化しています。かかる効果はナッジ理論が影響し、政策設計にも有益となっています。実験には、内的妥当性の確保が重視される一方で、外的妥当性に限界があるため、準実験や代表性のあるサンプル設計が今後の課題です。他方、実験の利点は、理論の精緻化と、国際的な共同研究が可能である点にあります。Behavioral Budgetingは文化的背景などの文脈依存の少ない研究分野として、国際協力の可能性を広げてくれます。
第二部では佐々木 周作氏(大阪大学 感染症総合教育研究拠点,特任教授(常勤))が「When Incentives and Nudges Meet-Promoting Budget Allocations for Undervalued Policies-」と題して報告しました。本報告では、日本の地方自治体の予算担当者を対象に、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン啓発キャンペーンへの予算評価に対する介入効果を検証しました。HPVは、皮膚や粘膜に感染するウイルスの一種で、子宮頸がんの主な原因とされています。HPVワクチンは、このウイルスの感染を予防し、特に若年女性の子宮頸がんリスクを低減する効果があるとされ、WHOなどの国際機関でも接種が推奨されています。介入は、国の補助金を強調する金銭的インセンティブ、他の自治体の実施を示すナッジ、両者の組み合わせの3種類です。行動経済学の観点から、伝統的な金銭的インセンティブの手法とナッジの効果を比較し、意思決定者である予算担当者に焦点を当てた点が新規の点です。実験は全国の自治体を対象に実施されました。参加者にはHPV啓発事業に関するシナリオを提示し、まず個人での評価、次に上司やチームと相談したうえでのチーム評価の2段階で予算配分額を記入してもらいました。介入は3種類設け、(1)国が費用の50%を補助するという金銭的インセンティブ、(2)他の自治体の実施状況を示す非金銭的ナッジ、(3)両者の組み合わせを提示し、対照群と比較しました。その結果、すべての介入群で、対照群に比べて予算額が大きく増加しました。特にナッジ単独の介入では、自治体自身が負担する「自己財源部分」の増額が顕著に確認されました。また、将来の効果を軽視しがちな予算担当者(時間割引率が高い人)ほど、介入の効果が大きく現れる傾向も見られました。本研究の意義としては三点を報告しました。第一に、従来の金銭的インセンティブと行動ナッジの効果を比較・組み合わせることで、それぞれの影響を実証的に明らかにした点です。第二に、対象を「市民」ではなく「政策決定者(予算担当者)」に設定し、社会的インパクトの大きい意思決定層に注目した点です。第三に、自己負担が求められる政策であっても、ナッジによって予算額を高められることを示し、今後の公衆衛生や長期的便益をもつ政策への応用可能性を示唆した点です。
第三部では、David Guo氏 (Wichita State University, Hugo Wall School of Public Affairs, Regents Distinguished Professor of Public Finance)が「Structuring Budget Simulations: Does Different Choice Outcomes Matter?」と題して報告を行いました。報告では、米国カンザス州セジウィック郡における「予算シミュレーション」プロジェクトについて紹介しました。報告者はウィチタ州立大学に着任後、地元行政と連携し、実務家と学術の橋渡しを目指しています。本プロジェクトでは、「Balancing Act」というツールを用いて住民が財政赤字を解消する方法を模索する参加型の予算シミュレーションを実施しました。この取り組みの目的は、市民とのコミュニケーションの促進、優先順位の可視化、内部予算プロセスの改善です。実験では、(1)財政赤字の初期額、(2)税負担の可視化、(3)支出調整幅を操作し、住民の選択に与える影響を検証しました。実験の参加者は、税金を増やしてサービス維持を選ぶ傾向があり、特に固定資産税の負担額を明示する設計が有効でした。一方、情報量などの制限への不満も見られ、次回の実験デザインの改良に向けた示唆が得られました。全体として、本プロジェクトは実験と現実をつなぐ貴重な試みであり、住民参加と財政教育の新たな可能性を示しています。 第四部では、Keynote SessionとしてTom Overmans氏 (Utrecht University, School of Governance, Public Governance and Management, Associate Professor)が「Budgeting Fast and Slow:Cognitive Bias in Public Budgeting」と題する講演を行いました。講演では、認知バイアスが予算判断に与える影響に関する行動科学的研究プロジェクトについて紹介されました。Tom Overmans氏は大学院時代に、参加者に社会保障番号などの下二桁を書かせたうえで、「その数字と同額をワインやチョコレートなどに支払うか」と尋ね、実際にいくらまで払うかを答えさせる行動経済学の研究論文に強い関心を抱きました。その論文では、大きな数字を書いた人ほど商品に多く支払う傾向があることが示され、繰り返しの実験でもこの傾向は確認されました。この知見からTom Overmans氏は、個人の私的な金銭判断だけでなく、公的部門における予算判断にも同様のバイアスが存在しうるのではないかと考えるようになりました。公的予算では他人の資金を扱うため、経済的合理性だけでなく、政治的合理性といった複数の合理性が関与します。このような複雑な意思決定環境において、行動経済学の知見をどう応用できるかが同氏の研究の出発点となりました。さらに予算に関する意思決定を単なる交渉や集団行動の結果と捉えるのではなく、行動科学の枠組みから再定義しようとしている旨を説明しました。 参加した約20名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。