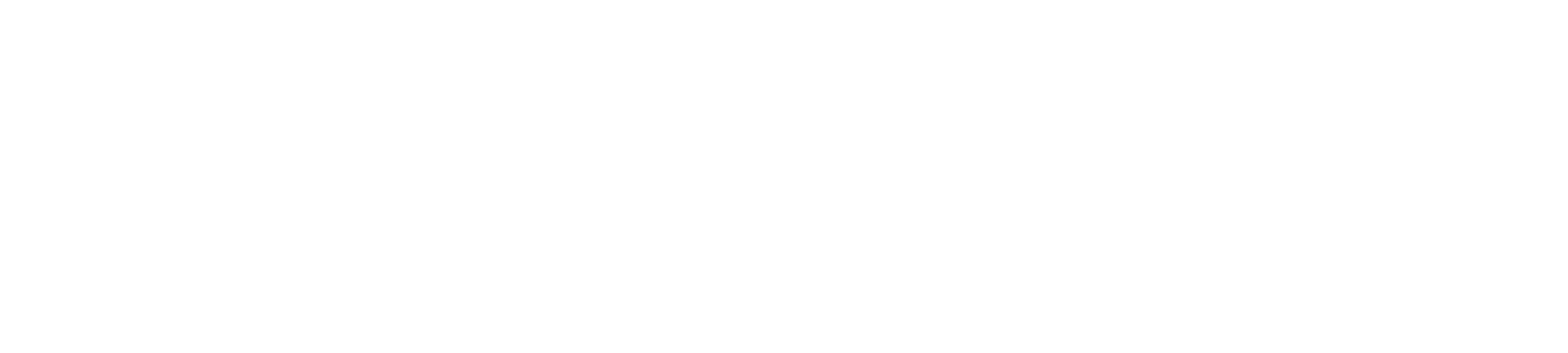京都大学経営管理大学院・経済学研究科は、令和6年6月9日に第105回京都管理会計研究会を総合研究2号館にて開催し、会場をZoomで中継するハイブリッド開催としました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、Lukas Goretzki氏(Professor of Management Accounting & Control , Department of Accounting, Stockholm School of Economics)より「Crafting qualitative research on management accounting and management accountants」と題して報告し、出席者と議論しました。このたびの報告者の招聘には公益財団法人牧誠財団の助成を受けています。
報告は以下の通り3部構成となっています。
第1部:EXPLORING THE INTRICACIES OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS’ IDENTITY WORK
第2部:AUTOMATING ACCOUNTING WORK IN SHARED SERVICE CENTERS – HOPES AND DISSILUSIONMENTS
第3部:CRAFTING AND PUBLISHING QUALITATIVE RESEARCH IN ACCOUNTING
第1部では、管理会計担当者のアイデンティティーについて報告しました。アイデンティティーは、社会、自己、他者との関わり、及び制度の4つの概念から構成されます。特に、他者との関わりを通じて機能するアイデンティティーはビジネス・パートナーとの結びつきが強いことを説明しました。ビジネス・パートナーの中でも代表的な者としてマネジャーがありますが、マネジャーから管理会計担当者に対して生産性や効率性を高めることへの要求が、管理会計担当者のアイデンティティーに大きな影響をもたらしていることを説明しました。また、デジタル化は管理会計担当者のパフォーマンスにとって功罪あり、デジタル化への不安がパフォーマンスを下げる可能性があることを指摘しました。
第2部では、スロヴァキアの会計業務を担うShared Service Center企業(以下「SSC」という。)についてのフィールドワーク研究の内容について説明しました。SSCでは自動化が導入され、導入時には従業員の中には不安を感じる人たちもいれば、導入に感激した人たちもいた旨を報告しました。このような従業員の自動化への関わり方を、Instinctive engagement、Calculative engagement及びCoerced engagementの3種類に類型化しました。Instinctive engagement は、従来のルーティン業務を改善するものとして自動化を能動的に従業員が受け入れる姿勢を示しています。Calculative engagementは、従業員が自動化を「投資」であり、なんらか金銭的や役職の点でメリットがあるものと認識して受け入れる姿勢を示しています。Coerced engagementは、自動化は選択肢ではなく、やむを得ずやらなければならいものと認識して受け入れている姿勢を示しています。本研究では、自動化がどのように従業員にとって繰り返し行う退屈な業務を克服し、組織において上述の3種のengagementが自動化にどのように相互に関係していくかを明らかにしている旨報告しました。
第3部では、会計学における質的研究方法について議論しました。質的研究では社会の現実をとらえるうえで適切な知識を有することを強調します。データは何も語らないので研究者によって解釈される必要があります。解釈は研究者の知識に影響されます。そして、「どうやって」「なぜ」という問いに集中します。リサーチ・クエッションの初めは個人的な問題意識からでも、データのとりやすさでもなんでも構いませんが、既存の先行研究との関係が論文を作成するうえでの重要なポイントになります。このように報告では先行研究に対する論文の貢献のあり方や、質的研究における理論の役割について議論しました。
参加した約20名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。