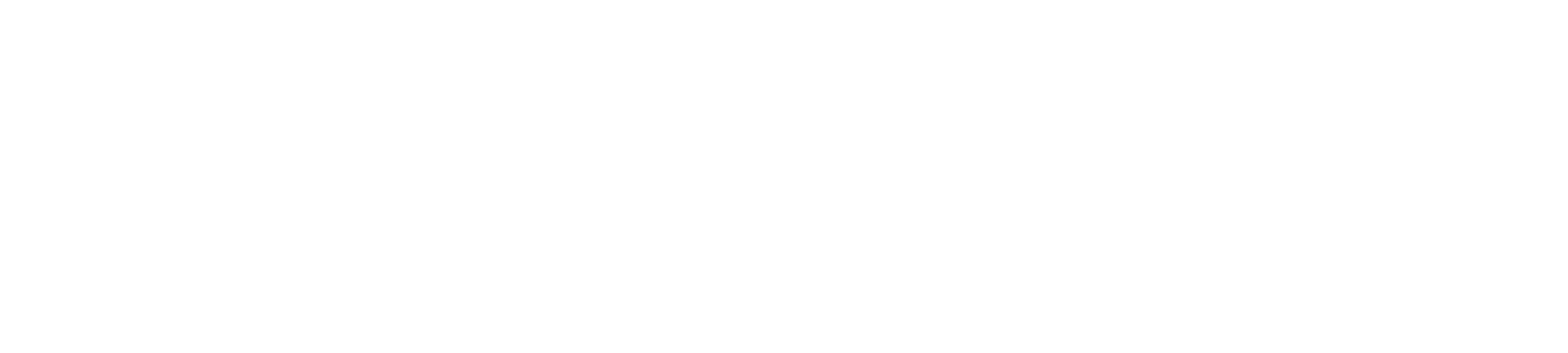日本管理会計学会2025年第1回関西・中部部会が、2025年6月14日(土)に京都大学(吉田キャンパス)を主催校として開催された。今回の部会も、対面とWeb(Zoom)を活用したハイブリッド開催となった。
プログラムにしたがって、特別講演1件及び自由論題報告2件の発表がなされ、活発な質疑応答が行われた。参加者は43名(対面28名、オンライン15名)であった。以下、特別講演、各報告の概要を簡単に紹介する。
第一部[特別講演] 司会:
講演者:野田 正史氏(株式会社プラス 代表取締役社長)
講演テーマ:「農業所得向上に貢献する 農産物直売所野田店舗経営」
特別講演では、株式会社プラス代表取締役社長の野田正史氏より直売所の経営を中心にお話を頂いた。はじめに、簡単に自社(株式会社プラス)の説明がなされた。店舗数は33店舗(和歌山17店舗 大阪府9店舗 奈良県6店舗 兵庫県1店舗)、登録している生産者数は9000名で本社は田辺市に構えていると説明された。そこからいくつかの店舗の様子を写真によって説明された。どれも工夫された店構えであることが写真から見てとれた。そして店舗の誕生のストーリーへと話が移っていった。1号店開業時に多くの苦しみを味わい、「手間ひまかけて作っても、JAや市場では他の人と同じ扱いされるのが不満だった」などもどかしさに悩んだという。
次にスーパーと比較したときの直売所の違いを述べながら、直売所を詳しく説明した。例えば、品揃えに関しては、スーパーは全て品揃えをしているのに対して、直売所はナショナルブランド(NB)を置かないことや、直売所は地元産が中心であり、肉魚はお店によって置いたり置かなかったりする。他に売れ残り品に関しては、スーパーでは自店舗が負担するのに対して、直売所では生産者が負担する。最後に比較から見える、直売所のメリット・デメリットを説明した。大きなメリットとしては、生産者にとって消費者の声がよりダイレクトに感じられるようになり、消費者の声がモチベーションになることであるのに対して、デメリットは、1店舗だと売れる数が限られると述べた。
またこうしたスーパーと直売所の違いを会計的な数値からも考察をした。損益計算書に目を向けると、人件費に大きな違いが見て取れた。スーパーは肉を切る人など加工段階など多くの人を要する一方、直売所はそういった人材を必要としないので比較的人件費が抑えられる。また、貸借対照表に目を向けると棚卸資産に違いがみられると説明した。これは、在庫リスクを直売所は負わないのに対して、スーパーは在庫リスクを負うことの違いによる。これらの違いから、直売所はスーパーよりも効率的な経営ができる可能性が高いと結論つけた。
講演後は、多店舗経営によるカーニバイゼーションの有無や、スーパーの中にある直売コーナと直売所の違い、直売所のより詳細な利益構造について、他の直売所との差別化のポイントなどの多くの質問があり、時間を余すことなく、活発な質疑応答が行われた。
第二部
講演者:矢野 厚登氏
講演テーマ:中小病院におけるマネジメントコントロールシステム
当日は、矢野 厚登氏()より「中小病院におけるマネジメントコントロールシステム」と題して報告し、出席者と議論しました。
ここでいう“マネジメントコントロールシステム(MCS)”とは、経営管理手法の総称であり、原価計算、BSC(バランスト・スコアカード)、予算管理などを含む仕組みです。
研究では、中小病院の6事業所の理事長・事務長インタビュー結果に基づく考察、病院のMCSに関するフレームワークの検討、および厚労省「医療施設経営安定化推進事業報告書」における17事業所の調査結果を分析しました。
分析結果は、中小病院におけるMCSは「会計・組織・文化・クラン」のパッケージとして機能しており、その実現には事務長の役割が極めて重要であることが示されました。事務長が、管理会計の知識と病院業務の理解を充実させた上で、経営会議に参加することで、トップ(理事長)と現場をつなぐ“連結管”としての役割を果たすことになり、これらの要素を備えることが中小病院におけるMCSの浸透、定着に寄与するということが示されました。
本研究は、「会計」「組織」「文化」「クラン」といった複数の要素は、大病院(一般企業でも同様の)のように”縦”で繋ぐ従来のMCSの構築ではなく
、一体となって“パッケージ”としてのMCSを構築することが求められるという新しい視角を提示したことで、中小病院がMCSを構築するための事務長の意識に貴重な示唆を与えるものになりました。
参加した約15名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。
第二部 (京都管理会計研究会第114回)
講演者:重田 直人氏(米国公認会計士 JUSCPAアカデミー客員研究員)
講演テーマ:”Relationship Between Outside Director and Corporate Value Improvement Strategy
当日は重田 直人氏(米国公認会計士(CPA)JUSCPAアカデミー客員研究員)により”Relationship Between Outside Director and Corporate Value Improvement Strategy”と題して報告し、出席者と議論しました。
ここでいう“Outside Director(社外取締役)” とは企業の経営陣から独立した立部からガバナンス機能を果たすものであり、経営者と投資家の間にある情報の非対称性を緩和し、もって財務諸表の質の向上を図る企業の役員です。近年、企業不祥事の多発を背景とし、日本企業におけるコーポレートガバナンス(CG:企業統治)の重要性が再認識されていますが、社外取締役の導入とその効果の研究は十分に行われておらず、企業価値の向上に資するのか着目しました。そこで、社外取締役の実効性と企業価値の向上の関連性を分析し、またそれ以外の要因が企業価値向上に影響をもたらすか分析を行いました。
サンプルは日本企業100 社のコーポレートガバナンス情報および世界の企業のTobin’s Q(企業価値指標)、ROE(自己資本比率)、OD比率(取締役全体における社外取締役比率)を分析しました。
分析結果は、社外取締役の比率が高い企業ほどTobin’s Q(企業の市場価値)が高いということが分かり、社外取締役比率が29%上昇すると、Tobin’s Qが0.27ポイント増加し、純利益とキャッシュフローの乖離によって定義される情報開示の質にも正の効果があることが示されました。また社外取締役が公認会計士(財務情報に精通している)か否かによって財務報告の質が向上するという仮説は否定されました。
本研究は、企業価値を高める戦略として、社外取締役の比率を高めることが有効であるということを示しているだけでなく、知的財産やR&Dといった価値創造因子の重要性にも示唆を与えるものとなりました。
参加した約27名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。