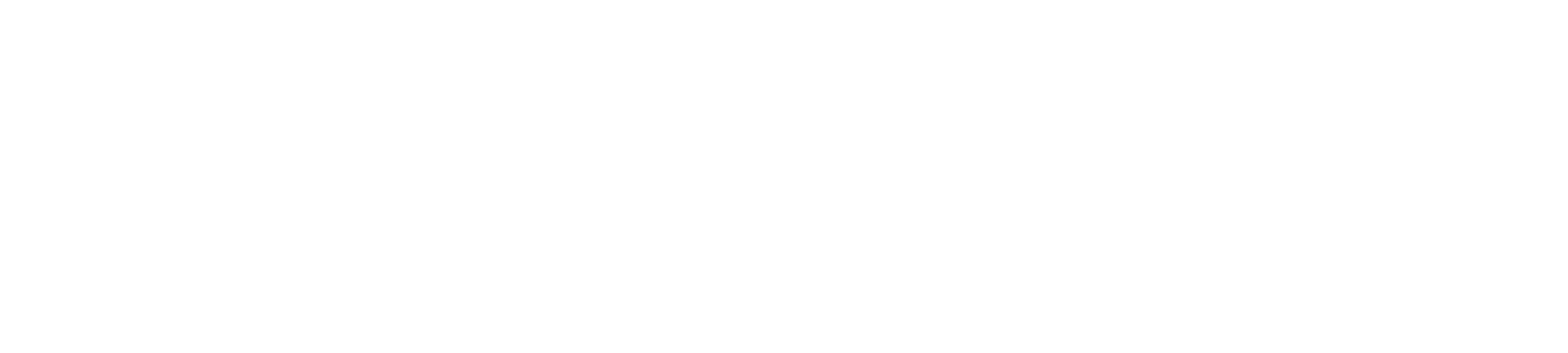京都大学経営管理大学院・経済学研究科は,令和7年3月8日に第111回京都管理会計研究会を総合研究2号館ケーススタディ演習室にて開催し、会場をZoomで中継するハイブリッド開催としました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、篠原巨司馬氏(福岡大学 商学部経営学科 教授)より「戦略実践としての管理会計 戦略管理会計の展開と経営計画の実践」と題して報告し、出席者と議論しました。
報告は、以下の通り3部構成となっています。
第1部:戦略管理会計の研究史・多様なアプローチ
第2部:経営計画の理論的検討
第3部:M社ケーススタディ‐戦略変更と管理会計制度の柔軟運用
第1部では、まず従来の管理会計研究において、戦略的意思決定に資する情報そのものに焦点が置かれていた一方、戦略形成プロセスを捉えようとする中で、その情報の利用スタイルに焦点が置かれるようになったと指摘しました。
静的アプローチから動的アプローチへ研究者の観点が変遷したことにより、経営計画の形骸化や目標の短期化など新たな課題が生まれていると指摘しました。
「形骸化」とは、(中長期)経営計画の時間的な拘束が従業員にとって意味をなしていない状態だと報告者は定義しています。 中長期経営計画を作っても組織成員が変化対応しない「絵に描いた餅」の状況を防ぐには、計画をインタラクティブに扱い、常に更新・翻訳していく柔軟性が必要だと指摘しました。
第2部では、経営計画の定義やプロセスについて先行研究の議論を紹介しました。経営計画における計画主義には、環境変化に対応できない硬直性や、計画自体に没入することで実質的に戦略的活動のリソースを削ってしまう問題が存在することを指摘し、経営計画がどのようにして柔軟性を確保し、かつ形骸化を防ぐかという課題を明確にしました。
この課題に対処する仕組みの一つに、経営計画の策定・修正に、自分たちの知見を反映する形で現場が参加する仕組みを紹介しました。現場が常時計画修正に関与することができる状態では、環境変化を早期に察知することができ、計画を更新する学習サイクルが回りやすい利点を挙げています。
また、現場の参加を促す要素として、経営層と組織成員における「信頼関係」があると指摘し、これは能力・誠実さ・意図の明確性によって高められると説明されました。
第3部では、コンサルティング企業M社の事例を通じて、形骸化していた中期経営計画が企業内の戦略と業績管理制度の変更を通じて機能した例を示しました。
当時M社は営業段階で算出した予測売上高を業績評価に利用していましたが、全社的な組織構造の変化や組織間の結びつきの変化に伴い、翌期の受注見込額を目標数値として算定するタイムスイッチ目標、受注に繋がった他部署への紹介が自部門の成果に反映されるトスアップ制度などを業績評価制度に付け加えました。
このような組織・業績管理の頻繁な変更に組織成員は対応できているのかという疑問に対して、制度設計段階には「ルール設定は経営方針のメッセージ」だという考え方を組織成員に周知し、運用段階には営業担当者による見積もりを管理スタッフがモニタリングすることなどを通じて、経営層と現場における信頼が構築されていると指摘しました。
また、M社の経営計画の会計的な本質として、ある期の数値目標に中長期的な数値目標が反映され、時間的拘束が生み出される仕組みとなっていることを指摘しました。
参加した約25名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。
参加者と議論する篠原氏