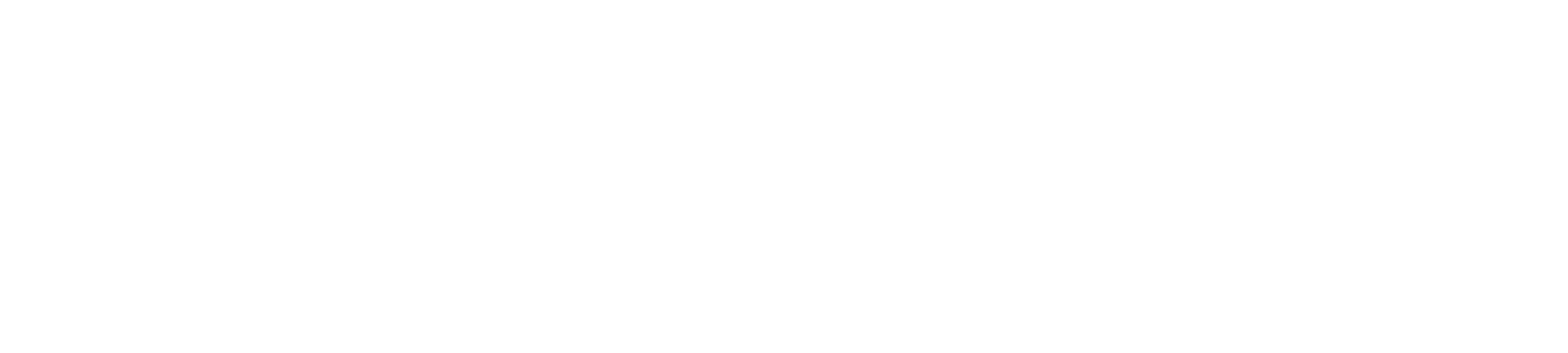京都大学経営管理大学院・経済学研究科は、令和7年1月11日に第109回京都管理会計研究会を総合研究2号館にて開催し、会場をZoomで中継するハイブリッド開催としました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、Sven Modell氏(Professor of Management Accounting、 Alliance Manchester Business School)より「Accounting in the New Space Age: Research Opportunities and Challenges」と題した報告があり、出席者と議論しました。このたびの報告者の招聘には公益財団法人牧誠財団の助成を受けています。
報告は2部構成で行われ、前半では、宇宙開発の概要や近年の動向、(管理)会計学との関わりが解説されました。直近20年前後では、技術革新や収益等を目的として政治的・商業的な宇宙利用への関心・投資が高まり、今後も市場規模の拡大が見込まれています。一方で、宇宙開発には、固有の論点が存在することが指摘されました。具体的には、重力や宇宙の過酷な環境といった実践上の課題に加えて、特に宇宙に関する知識が不足していることや、宇宙とのタイムリーな情報の共有ができないこと、国際的な法や制度的枠組みといった規制環境に不透明さが残ることによって、意思決定上の不確実性が存在するとされています。会計学的には、こうした経済的、政治的不確実性を踏まえた投資意思決定や業績評価、リスク管理の在り方など、多岐にわたる問が存在するとのことです。
後半では、特に宇宙開発におけるコストの膨張要因に焦点を当て、既存研究を拡張することの必要性が主張されました。宇宙開発のコストが膨張しがちであることは広く認識されており、その要因に関する先行研究が蓄積されています。一方で、検討される要因の大半はすでに十分な知識や人為的な調整の可能性があり、知識が不十分である要因や、人為的な調整ができない要因の検討が不十分であることが指摘されました。既述のとおり、宇宙について未知の事柄が多いことや、制度的な不確実性が高いことを踏まると、宇宙開発において、知識や人為的な調整の可能性が不十分な要因の検討の重要性は高いと考えられます。報告の終盤では、知識も調整可能性も不十分な事象として、宇宙(地球以外の天体)での資源の開発や地球外生命体の権利保護を挙げ、これらを考慮する場合に、会計的なコスト管理にいかなる影響がもたらされるかという思考実験が議論されました。宇宙資源の開発に関しては、既存の資源ビジネスから類推すると、コストが上振れすることを懸念する勢力が組織内で生まれるため、コストの膨張が抑えられる可能性がある一方で、地球外生命体の権利保護については、動物の権利保護から類推が行われ、倫理的義務感からコストが膨張しやすくなる可能性が指摘されました。
参加した約17名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。
目次