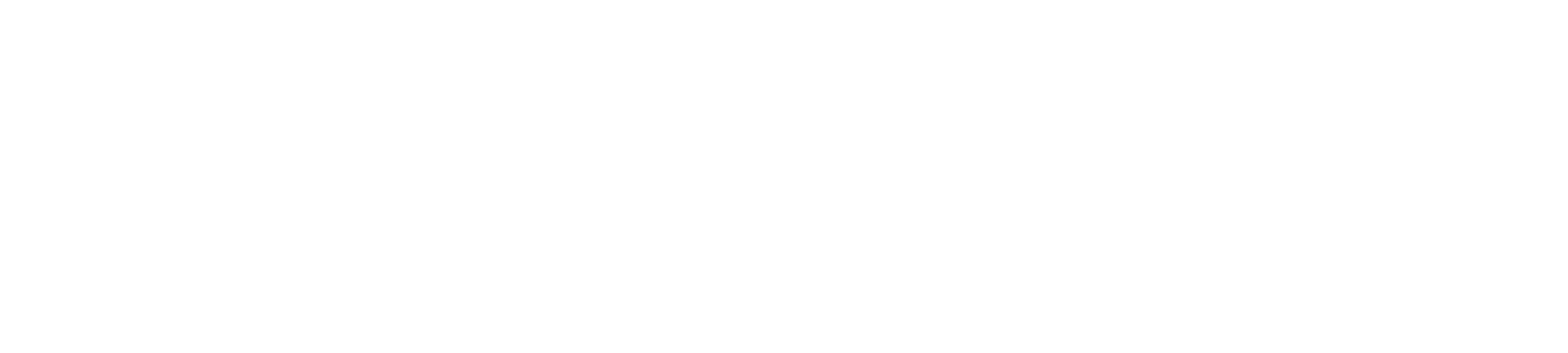京都大学経営管理大学院・経済学研究科は,令和6年11月9日に第107回京都管理会計研究会をZoomにてオンラインで開催しました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。
当日は、繁本和宏氏(香川大学経済学部 准教授)より「社債投資家から見た財務情報報告の現状と課題:格付のミクロ的視点からの現状分析」と題した報告があり、出席者と議論しました。
報告では、我が国における社債取引の低調さや関連するデータの入手困難性を背景としてか、財務情報利用者としての社債投資家への関心が低い一方で、金融政策の転換(金利の上昇)に伴う社債投資家への財務報告の重要性が高まっていることを指摘しました。しかし、社債投資における財務情報の利用は投資戦略に依存し、必ずしもすべての社債投資家が財務情報を重視するわけではないことから、本報告では、2000年代終盤に情報開示が拡大した格付会社による財務情報の利用に注目し、社債投資家における財務情報の重要性を検討しました。
検討に際して格付各社が財務リスクの分析に適用する基準を分析し、格付においては、財務指標と事業リスク等の定性的な情報を結び付けつつ、特に有利子負債とその返済原資のバランスを重視して将来の債務償還能力が評価されていることを明らかにしました。
続いて、テキスト分析という文書の分析手法について、その理論的基礎や意義について言及したうえで、格付の公表に際して格付各社が発行する文書(格付リリース)のテキスト分析についても報告が行われました。分析の結果、格付において返済が必要な債務、返済原資の稼得力、稼得力向上において取り得るリスク耐久力の3点が重視されていることを示し、格付の基準において重視されている観点が実際の格付評価にも適用されていることを確認しました。
さらに、格付リリースを格付け水準別に分析した結果も示されました。格付が高いほど財務的な健全性が前提化し、将来の収益力がより注目され、逆に格付が下がるごとに財務的な健全性に重点が遷移していく一方で、極端に格付が低くなると足元の業績や資金繰り、短期的な債務償還能力が重視されるようになる傾向が明らかとなりました。こうした結果から、社債投資家の求める財務情報が、社債発行主体の経営状態によって変化することを示唆するものであることが指摘されました。
また最後には、財務報告に対する社債投資家の要求を踏まえた望ましい会計基準という規範的研究への展望も示されました。
参加した約13名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。