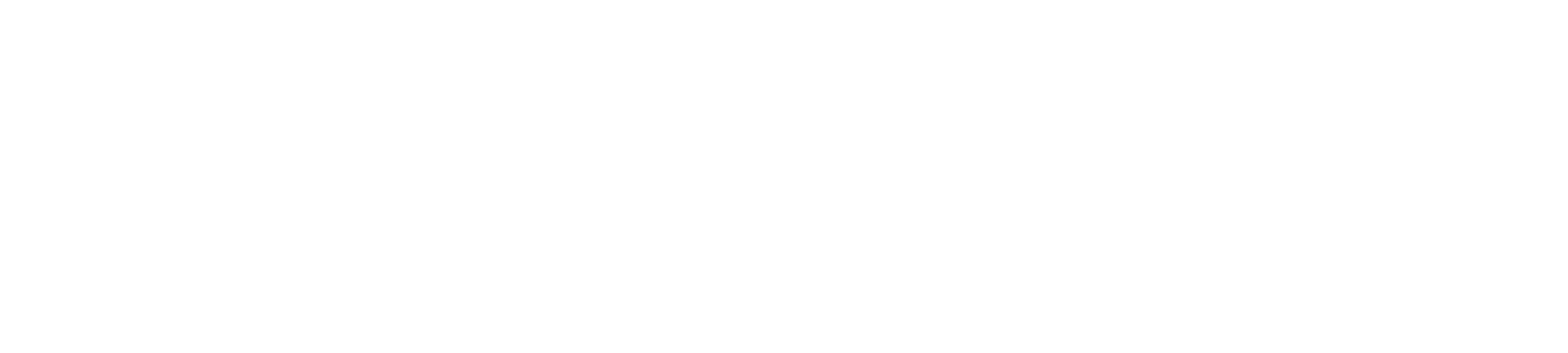| 京都大学経営管理大学院・経済学研究科は、令和6年6月8日に第104回京都管理会計研究会をオンラインによるZoomで開催しました。本研究会は、研究者・実務家・院生を対象に管理会計研究の最先端の研究成果について知見を共有することを目的にしています。 当日は、若林靖永(京都大学名誉教授(哲学的企業家研究寄附講座客員教授))氏より「会計専門家あるいはCFOがおさえておくべき21世紀のマーケティングの課題」と題して報告し、出席者と議論しました。 報告は、前半部と後半部の2部構成となっており、前後半それぞれに提示された3つの問いに答える形で、経理・財務だけではなく、今後事業戦略の要となるべき会計専門家あるいはCFOがおさえておくべき現代のマーケティングにまつわる新しい視点を紹介しました。 前半部は、既存市場のマーケティングのありように着目し、「マーケティングとは?」、「プロダクトライフサイクルでみるマーケティング戦略とは?」、「既存事業の、成長を目指すマーケティング戦略とは?」と題する3つの問いに答える形で議論を行いました。マーケティングの祖、フィリップ・コトラーによれば、マーケティングは消費者目線から製品と価値を生み出して他者と交換を行うことに重きを置いていた。一方、21世紀のマーケティングは、世界をよりよい場所にすることを目的とし、企業を取り巻く全てのステークホルダーと共有可能な社会的意義を果たす役割が明確になっているかどうかが肝要だと説明しました。マーケティング戦略においては、環境・事業・製品ごとに適切なターゲティングとフレームワークの使用を行うことが肝要であることを示しました。 後半は、「撤退・縮小のマーケティングとは?」、「価値創造とは?」、「新市場創造のマーケティングとは?」と第する3つの問いに答える形で議論を行いました。価値創造は企業が創造する、という従来的な考え方から、企業と顧客が価値を共創していく、という今日的な価値創造の考え方に基づき、多様な顧客のニーズを細分化し、透明性のある信頼関係を顧客と構築する重要性を強調しました。 また、新市場創造のマーケティングに関しては、最小限のコストで段階的に製品・サービスを開発する「リーンスタートアップ」と呼ばれるアプローチ手法や、所与の手段から始めて積み上げ式に新しいゴールを発見していく「エフェクチュエーション」と呼ばれる思考法を紹介したうえで、それぞれの一長一短を取り上げ、場面に合わせて柔軟に使い分ける必要性を強調しました。 参加した約50名の研究者・院生や実務家などと講演者との間で活発に議論が交わされ、盛会のうちに終了しました。 |
目次